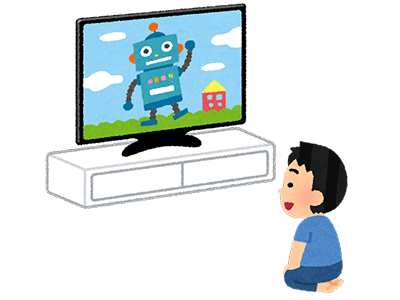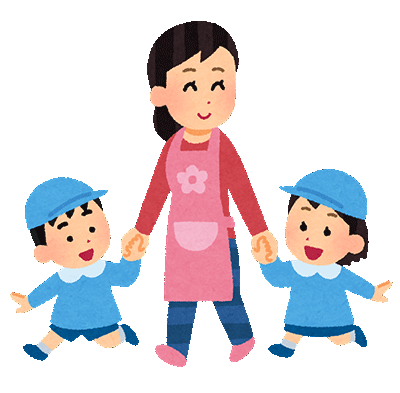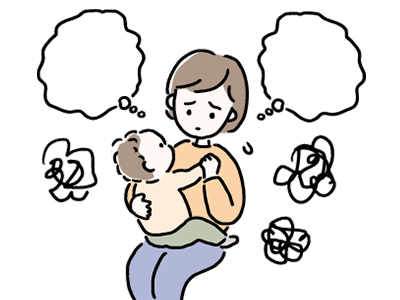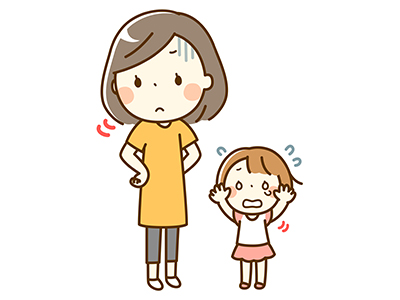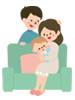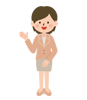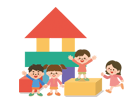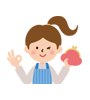お子さんとおうちで過ごす時間、マンネリ化してTVや動画を見る時間が長くなってしまい、悩んでいらっしゃる親御さんは多いかと思います。
今回は、年齢別に、親子でおうちで楽しめる簡単な遊びをご紹介しますので、よかったら試してみてくださいね♪
【0~1歳…布を使ってみましょう】
布が1枚あることで、赤ちゃんはいつもの遊びも新鮮に感じます。布を使って「いないいないばぁ遊び」や「かくれんぼ」。フリフリ振りながら「追いかけっこ」やお尻に付けて「しっぽ取りゲーム」など、ねんねの年齢~はいはいやたっちの年齢までいろいろな遊びができます♪
※布を使って遊ぶときは窒息・誤飲の危険がないよう、最後に片づけるまで親御さんが目を離さずお見守りください。
【2~3歳…新聞紙を使ってみましょう】
新聞紙は手先や体全体を使った遊びに大活躍!
新聞紙をビリビリ破く→丸める。これだけでも、手指の発達を促します。
その後、的に当てたり、箱に入れる「バスケットボールごっこ」!
最後にはビニール袋に入れてお片付けも遊びながら出来ますよ♪
【3~4歳…新聞紙遊びを発展させて】
だんだんと手先が器用になり、想像力が発達してくるこの年齢にも新聞紙はぴったりです!新聞紙を折る、ハサミで切るなどして服やベルトを作ることで、微細な手指の動きの力を育てます。さらに、棒状にして剣に見立てて鬼滅ごっこなど、なりきり遊びでストレス発散も。
【5歳…さらに高度なゲームや工作も】
・新聞紙1枚で親子でジャンケンゲーム
それぞれ、広げた新聞紙の上に立ちます。じゃんけんで負けたら新聞紙を小さくたたみ、その上に乗ります。乗っていられなくなったら負け!忍耐力や身体バランスが鍛えられます。
・段ボールや箱を使って、ビー玉ころがし
お菓子などの空き箱の中に、セロハンテープなどで小さく切った厚紙などの障害物を付けていきます。付け終わったら、ビー玉を端から端まで転がせるか、チャレンジ!
いかがでしたでしょうか?身近にあるもので、いつものおうち時間が、子どもにとっては特別な時間に変わります。新聞紙を使った遊びなどは、年齢の違うごきょうだいも皆で楽しむことができますので、時には思い切り散らかしてもよい日をつくって遊んでみてはいかがでしょうか?
※誤飲やけがにご注意の上、大人の見守りのもとで遊んでください。
松島町児童館でも、いろいろな室内遊びを楽しむことができます。各種イベントも開催していますので、ぜひ遊びにきてくださいね♪
松島町児童館はこちら