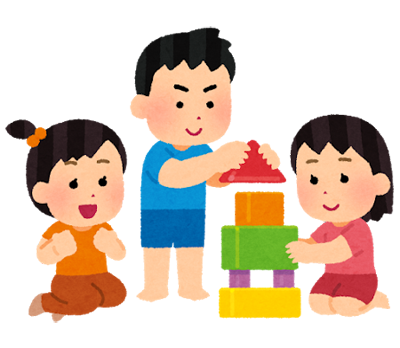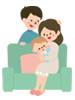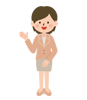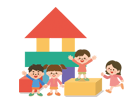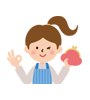どうしたらいいの?トイレトレーニング

トイレトレーニングについて悩むお母さんは大変多いと思います。
おむつが外れる時期は個人差がとても大きいので、年齢などにとらわれず、お子さんの様子を見ながら進めましょう。
【時期について】
トイレトレーニングを始めるタイミングは、お子さんの体と心の準備が整った頃が始める目安です。具体的には、
①おしっこの間隔が2時間以上空くようになった。
②上手に歩けるようになった。
③言葉が話せるようになった。(トイレしたいという意思表示ができるようになった)
このような成長段階になってきたら、トライしてみてもよいでしょう。
【トレーニングための工夫】
お子さんにとっても、おむつ以外にトイレをするのは初めての感覚で、トイレは狭く怖い場所に見えてしまいます。
また、トイレは子どもにとっては大きく、足が床に着かないため、いきみにくいという問題もあります。最初は、おまるや補助便座を使い、トイレをお子さんが好きなキャラクターで飾り、トイレに行きやすい環境を作りましょう。また、何回もトイレに連れて行くと、段々トイレに行くのがイヤになる子もいます。
おむつにしてもいいよと、言ってあげるのも一つです。トイレで出来たときは、いっぱい褒めてあげてください。
トイレトレーニングには失敗はつきもので、後戻りすることもあります。保護者の皆さんが焦ってしまい、イライラしたり、叱ってしまうと、なかなかトイレトレーニングが進まないということもあります。「おむつが取れない子はいない」と、無理せず進めていきましょう。
お子さんの成長や育児に関する悩みは、お気軽にこちらにご相談下さい♪